
外国で親しまれている子供の遊び5つ
よく調べられているキーワード

「小学校に入学した頃は授業についていけたのに、3年生になったら急にわからなくなってしまった」というような場合、単に教科の難易度の問題だけではなく、“子供の理解力不足”という大きな壁が立ちはだかっていることが多いといわれています。
実は、子供の理解力を育てることは、小学校からではなく、幼児期からすでにはじまっています。
では、子供の理解力はどうすれば育てることができるのでしょうか?
『国語が得意科目になる「お絵かき」トレーニング』の著者である坂本聰先生に、子供の理解力を育てる方法についてインタビューしました。
「お絵かき」トレーニングとは、「絵を見て文を書く」「文を読んで絵を描く」という作業を繰り返し行うことで、国語の基礎となる理解力を育てるトレーニングのことです。一体どのようにトレーニングを行うのか、なぜ理解力をつけるためにお絵かきトレーニングが有効なのかなどについて、詳しく伺いました。
目次

「お絵かき」トレーニングは、子供が何をわかっていて、何がわかっていないのかを発見するためのトレーニングです。
トレーニング自体は小学2年生ぐらいからはじめるのですが、実は幼児期からの親と子の関わり方が、学童期の理解力に深く関わっています。そのため、幼児期の取り組み方についても、後ほどお話ししたいと思います。まずは「お絵描き」トレーニングがどんなものかということについて、ご紹介しましょう。
「お絵かき」トレーニングのやり方はとてもシンプルで、絵を見てその内容を文章で説明することと、文章を読んでその内容を絵で描くことです。
絵を見てその内容を文章にするトレーニングでは、たとえば下にあるような木の絵を見せて「絵の中にあるものは何?」というように、絵に描かれた内容を文章で説明してもらいます。
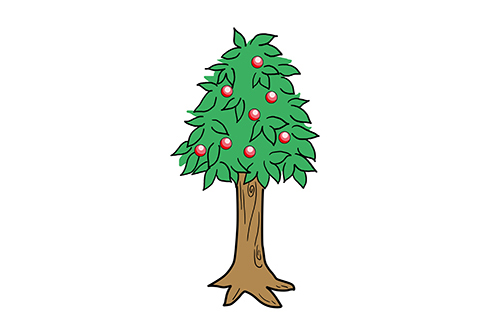
すると、「木があります」という文章を書く子もいれば、「赤い実がなっている木があります」と書ける子もいます。このときに、最初の子には「絵の中の赤いものはなあに?」と聞いてあげるなど、絵の中にあるものをいっしょに確認していくことによって、知らないもの、わかっていないことに自ら気づくことができます。
このように絵の中に知らないものがあれば、当然文章にすることはできないので、子供は「自分は何がわかっていなかったか?」ということに気づき、わからなかったことを教えてもらうことで「理解する」という体験をすることができます。
また、子供に文章を見せて、その文章からイメージする絵を描くトレーニングも行います。
たとえば「これは、ふさふさとした葉の中に赤い実がなっている木です。」という文章を見せて、絵を描いてもらいます。
文章の中に知らない言葉があると、絵の中に描くことはできません。そのため、自然と子供は「これは何?」という質問をするようになります。そのわからないポイントをしっかりと拾ってあげることが、お絵かきトレーニングでは最も大切です。
どんな絵を描くか、どんな文章を書くかというのは一人ひとり違うので、「お絵かき」トレーニングには正解がありません。ドリルのように正解をチェックして終わりではないので、親が子供のために時間を作り、いっしょに向きあって行う必要があります。
親と子がいっしょに向きあう時間を作るというのは、とても大変なことかもしれません。でも、この「親と子が向きあう時間を作る」ということは、どの年代でも非常に大切なことだと思っています。
お絵かきトレーニングは小学校2年生ぐらいからはじめるのですが、実は幼児期からの親と子の関わり方が、学童期の理解力を決めると言っても過言ではありません。
では具体的にどう関わるのかというと、子供が何か言葉を発したときに、親がそれに向きあってあげることが特に大切なことです。
幼児はまだ語彙が少ないので、自分の気持ちを言葉で伝えることが難しく、何を言っているのかもよくわからないときがあります。そのため、親もつい「うんうん」と言いながら話半分に聞いてしまって、そのままにしてしまうこともあるでしょう。でも、そこを大人が真正面から向きあってあげることによって、子供の理解力を育てることができるのです。
保育園や幼稚園から帰ってきたときに、子供は絶対に親に話がしたいわけですよ。とりあえず今日起きたことを話したいし、知っていることや覚えたことを話したいのだけれど、思いついたことからバッと言いだすから、親としては何のことかよくわからなかったりします。
たとえば「今日〇〇ちゃんに叩かれちゃった」というような話を、突然してきたりすることもあります。そういったときに、どうしてそうなったのかをちゃんと聞きだしてあげないといけません。
じっくりと子供の話を聞いてあげると、「最初は仲良く遊んでいたけれど、おもちゃの取りあいになって、自分が先に叩いたら、自分も叩かれちゃった。でもそのあと仲直りしてたくさん遊んだ」というようなストーリーがわかってきます。こうして親が子供の話に向きあってあげることで、子供は頭の中が整理されてくるのです。
こうして子供の話をじっくりと聞いてあげた後、「どんな風に遊んでいたのか、絵に描いてみて」と言うと、子供はけっこう大喜びで描きますよ。それがのちのちの「お絵かき」トレーニングにもつながっていきます。
もちろん小学生のような具体的な絵は描けませんが、子供自身にはわかっているので、絵を指さしながら説明してくれるでしょう。
子供が保育園から帰ってくる時間帯は、親御さんも夕食の準備などで、とても忙しい時間だと思います。子供の話を聞いてあげるのは大変だと思いますが、たとえ10分でも15分でも良いので、子供の話に耳を傾けてあげましょう。
常に言葉を整理していくことが習慣になっていく子と、その機会がない子とでは、小学校に上がった頃に理解力に大きな差が出てきます。
すべての勉強の基礎は理解力なので、幼児期にその基礎である「しっかり向き合ってお話しできる」という習慣をつけてあげることは、とても重要です。

1番よく話にあがるのは、小学校3~4年生ぐらいになって、学校の教科書のボリュームが増え、算数の文章題が登場するタイミングです。
教科書は1~2年生と3年生とでは難易度に大きな開きがあり、1~2年生の段階で順調に理解力が育っていない子は、3年生頃から学校の勉強についていけなくなります。
でも実はそれは小学校よりもっと前の段階で、親が子供としっかり向きあって会話をしていたかどうかが、大きく影響しています。言葉で親に何かを説明したり、親から説明されたりした習慣があった子供は、理解力が順調に育っていきます。
親だけでなく、幼児期の子供が長時間過ごす保育園や幼稚園の存在も、意外と重要です。子供に真正面から向きあってくれる園と、そうではない園があり、どのぐらい向きあってくれたのかによって理解力に差が生まれます。
たとえば幼児期に子供は「なんで?なんで?」としきりに質問をしてきますが、そのときに大人は面倒がらずに、子供としっかり向きあってあげることが大切です。
もし親が忙しくていい加減な対応をすると、子供はやがて「なんでっていうのは、あまり言っちゃいけないのかな?」と思いはじめます。子供が「なんで、なんで?」とだんだん言わなくなるのは、そう言うと大人から嫌な顔をされるからです。
そうなるともう、「ドリルのような与えられたものを、ただやっていれば良い」という考え方になってしまい、そのまま大人になってしまうのです。
今は物事に疑問をもつことができない大人が多く、自分自身が成長してからそれに気づき、理解力を育てるためのトレーニングを行う人もいます。
私自身も、高校時代にベルギーに留学したことを契機に、自分に理解力がなかったことに気づきました。わかっていると思っていたけれど、実はわかっていなかったということに、気づいたんですよね。
それまで日本の学校でフランス語の勉強はある程度やっていたので、「フランス語が聞き取れれば授業はわかるだろう」と思っていたのですが、実際は聞き取れてもわからないことに気がついたのです。
日本語だと何となく聞いて、その場でわかったような気がしてしまうのですが、外国語の場合はそうはいきません。フランス語でわからない単語があれば辞書で一生懸命調べたのですが、辞書で調べているのに「あれ?わからない」。最初はわかっても、ちょっと違う方向から聞かれた問題には、答えられないのです。
「じゃあどうすればわかるのだろう?」と思ったのが、のちに国語力の育成を目的とした個別指導教室・考学舎を立ち上げたきっかけとなっています。

子供が「これなに?」と質問したくなるようなタイミングを、数多く作ってあげることが大切だと思います。
たとえば食事の場面で、「あれ?これは何?」と聞きたくなるような料理をだしてあげたり、子供がいろいろな発見ができるような場所に連れていってあげるのも良いでしょう。
スーパーにいっしょに出かけたときも、珍しい野菜を見つけたりすると、子供はしきりに質問してきます。
そのときに、親は適当に答えずに、しっかりと向きあって答えてあげることが大切です。
子供に質問をされたときに、たとえ答えてあげられないことがあっても、「親なんだからちゃんと答えてあげなきゃ」と思う必要はありません。わからなかったら、スマホでいっしょに調べれば良いのです。
そういう子供にとって「知らない」「わからない」タネを、いろいろなところに蒔いてあげましょう。
理解力や考える力を育てる上において、未就学児であっても「子供と自分は別人」ということを親が認識できるかどうかも、大きなポイントだと思います。
自分と子供を同じように考えてしまうと、つい「これはわかっているはず」と思ってしまいますが、あくまで別人だと思えば「ちゃんと説明してあげなければわからない相手だ」と思うことができます。
たとえば子供に「幼稚園で何をしてきたの?」と聞くときも、自分がわかっていると思って聞くのと、別人だと思って聞くのとでは全然違います。
別人だと思っていれば「知らないのだからちゃんと聞きたい」と思いますが、自分がわかっていると思うと、聞いている途中で「あなたそれこうでしょ?ああでしょ?」と言ってしまったりします。
そうではなくて、子供には自分の知らない世界があり、別の人間なんだということを、親がどれだけ認識できるかが、理解力や考える力を育てるためにとても重要です。
子育てというのは、親と子が離れていくトレーニングなのかもしれません。生まれたときが1番近く、少しずつ離れていき、どこかの時点から一定の間隔を保った距離感で続くことになります。それができずに、親子の一体感を引きずったまま小・中・高と成長してしまうと、大変なことになります。
少なくとも子供が社会に出るぐらいまでは、親は少しずつ離れていく努力が必要でしょう。
小学生から大学生、社会人まで、さまざまな年代の人の理解力を育てるために活動されている坂本先生。
「理解力が育たないまま成長した学生も、親以外の誰かが本気になって向きあうことで、必ず変わっていきます」という言葉が、とても印象的でした。
昔は親が忙しくても、近所の人などいろいろな人が子供と向きあってくれましたが、今はそういう地域社会もなくなってしまいました。だからこそ、親や先生など、誰か大人が子供にしっかりと向きあってあげることが、なおのこと必要なのかもしれません。

プロフィール:坂本 聰(さかもと さとし)
考学舎代表。
1972年東京都生まれ、一橋大学商学部卒業。大学やサラリーマン時代に「思考力、コミュニケーション力」の重要性を痛感する。99年、国語指導をベースにした現代の寺子屋、考学舎を設立。高校在学中にベルギーに留学した経験などをふまえ、小学生から大人まで、系統的に思考力を育成する独自のカリキュラムを提供している。
「世界が身近になる新聞トレーニング 時事学」主宰、昭和医療技術専門学校特任教授(日本語表現法、思考法)、他、専門学校、大学等での講義講演多数。
主な著書に『国語が得意科目になる「お絵かき」トレーニング』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『お絵かき作文ドリル(基礎編・チャレンジ編)』(朝日新聞出版)がある。
時事学Webサイト
考学舎Webサイト













外国で親しまれている子供の遊び5つ

しりとりで子供の英語力がアップ!ゲームで楽しく英単語を覚えよう

よく使われる英語の自己紹介フレーズ7つ

【専門家に聞く】子供を幸せにする魔法の言葉!自己肯定感を高めれば頭の良い子に育つ?!

英語で自己紹介してみよう!簡単なフレーズから始める子供の英会話

子供の英語教育はどの方法がベスト?自宅と教室の学習方法を徹底比較

外国の子供は英語のスペルをどう覚える?効果的な学習方法をご紹介!

英語の挨拶のフレーズがぐんぐん覚えられる動画5つ!

子供英語教育にオススメ!国際交流ウェブサイトをチェックしてイベントに参加してみよう!

子供の学力は家庭環境で決まる!遊びながら知的好奇心を伸ばす方法とは?

新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

ハイハイはいつから?早い子は5カ月頃?練習方法やしない原因、注意点をご紹介

いつから赤ちゃんを自転車に乗せられる?前乗せ?後ろ乗せ?抱っこ紐は?

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

赤ちゃんとのお散歩、いつからOK?最適な時間帯や注意点

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

英語の「美味しそう」は使い分けが大切!3つの異なる表現方法とは

お誕生日は英語メッセージで!1~3歳も英語でお祝いしよう!

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ
© Disney © Disney/Pixar
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and
E.H. Shepard.


外国で親しまれている子供の遊び5つ

しりとりで子供の英語力がアップ!ゲームで楽しく英単語を覚えよう

よく使われる英語の自己紹介フレーズ7つ

【専門家に聞く】子供を幸せにする魔法の言葉!自己肯定感を高めれば頭の良い子に育つ?!

英語で自己紹介してみよう!簡単なフレーズから始める子供の英会話

子供の英語教育はどの方法がベスト?自宅と教室の学習方法を徹底比較

外国の子供は英語のスペルをどう覚える?効果的な学習方法をご紹介!

英語の挨拶のフレーズがぐんぐん覚えられる動画5つ!

子供英語教育にオススメ!国際交流ウェブサイトをチェックしてイベントに参加してみよう!

子供の学力は家庭環境で決まる!遊びながら知的好奇心を伸ばす方法とは?

新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

ハイハイはいつから?早い子は5カ月頃?練習方法やしない原因、注意点をご紹介

いつから赤ちゃんを自転車に乗せられる?前乗せ?後ろ乗せ?抱っこ紐は?

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

赤ちゃんとのお散歩、いつからOK?最適な時間帯や注意点

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

英語の「美味しそう」は使い分けが大切!3つの異なる表現方法とは

お誕生日は英語メッセージで!1~3歳も英語でお祝いしよう!

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ
