
新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン
よく調べられているキーワード

ひとりで赤ちゃんをお風呂に入れるのは、なかなか大変。お悩み中のママ・パパのために、ワンオペお風呂のコツやテクニック、あると便利なグッズなどもご紹介します。事故やスキンケア、水分補給などの注意点もチェックしてみてください。
目次

「ワンオペお風呂」とは、親がひとりで赤ちゃんをお風呂に入れることをいいます。「ワンオペ」は、ワンオペレーションの略。もともとは、飲食店などで店員がひとりで店を切り盛りすることを指してできた言葉ですが、そこから派生して、ワンオペお風呂やワンオペ育児といった言葉が生まれました。
核家族化が進んだことや共働き家庭の増加などにより、ママまたはパパがワンオペで育児を行うケースは少なくありません。中でも、とくに大変なのがお風呂といえるでしょう。
一般的には、生後1カ月頃まではベビーバスなどで赤ちゃんを洗う沐浴(もくよく)を行い、1カ月健診で医師の入浴許可が出てから家のお風呂に入れることが多いようですが、赤ちゃんのお風呂デビューに手を焼くママ・パパたちは多いもの。
「準備が大変!」、「自分の体がゆっくり洗えない」、「泣いたり暴れたり。ワンオペお風呂はいつも修羅場」、「お風呂が終わるたびにどっと疲れて夕飯の支度が辛い!」などなど、切実なお悩みが聞かれます。
安全にも気を使わなければならない赤ちゃんのお風呂問題に試行錯誤している方も多いでしょう。
ここからは、ワンオペでもスムーズに赤ちゃんを入浴させる方法や段取りを詳しくみていきます。

生まれてから日々めざましく成長する赤ちゃん。首も腰もすわっていない新生児期を過ぎたばかりの頃は、とくに大変に感じる方も多いようです。我が子の成長に合わせ、入浴法を変えたり工夫したりすると、ワンオペお風呂が少し楽になるかもしれません。ここでは、赤ちゃんの月齢や成長・発達段階の視点から、入浴のコツや洗い方の一例をご紹介します。
赤ちゃんの成長具合には個人差があります。月齢だけでなく、お子さまの様子をよく観察し、その時々の状態に合った方法を取り入れてくださいね。
新生児期の赤ちゃんは、ベビーバスなどにお湯をため、沐浴によって体を洗います。へその緒が取れて完全に乾くまでは、雑菌から守るためにも専用のベビーバスを使用し、産院などで指導された手順で沐浴を行いましょう。新生児は肌が弱いため、柔らかいガーゼを使い、ベビーソープなどで全身を丁寧に洗ってあげてください。
首をしっかり支え、せっけんなどで手が滑らないように注意しましょう。はじめてのお風呂に驚いてしまう赤ちゃんも多くいます。ママ・パパが優しく声をかけながら、10分〜15分を目安に手際よく入れてあげると良いでしょう。
また、沐浴をはじめる前に赤ちゃんのお着替えの準備をしておくことが大事。肌着のひもやボタンは外し、着せやすいように重ねてセットしておくとスムーズです。バスタオルはお着替えの上に置いておき、お風呂から上がったら素早く全身を拭いて、湯冷めしないように注意しましょう。
新生児期を過ぎ、1カ月健診で入浴許可が出た頃からお風呂デビューもOK。ワンオペでいっしょにお風呂に入る際は、赤ちゃんをバスマットやバウンサーなどに乗せて脱衣所で待機させ、先に大人が体を洗ってから赤ちゃんの体を洗い、いっしょに湯船につかります。首がすわるまでは、湯船の中でも首の後ろをしっかり支えるようにします。
赤ちゃんを外で待機させず、最初からバスルーム内にバスチェアなどを置いておく方法もあります。季節や状況に応じて入れ方を選ぶようにすると良いでしょう。
慣れないうちは赤ちゃんのお着替えにも時間がかかり、何かとアタフタしがち。お風呂上がりに、大人がサッと羽織れるバスローブを用意しておくと、すぐにお世話に取りかかれます。生後3カ月頃になると体重が出生時の約2倍になり、ずっしりとしてきます。赤ちゃんを抱きかかえたまま足を滑らせたり転んだりしないように注意しましょう。
また、大人が入浴中のときも、見える場所に赤ちゃんを待機させ、目を離さないようにしてください。
生後3カ月を過ぎると、首もすわり、足の筋肉もだんだん発達してきます。バスルームでは、向かい合うように赤ちゃんを抱っこして洗ってあげましょう。寒い時期には、座面のくぼみに浅くお湯が張れるバスチェアなどに座らせて洗ってあげてもOK。生後5カ月頃になると、おもちゃを握ったりする子も増えてくるようです。お気に入りグッズがあると、機嫌良くお風呂に入ってくれるかもしれません。
おすわりができると、バウンサーやバスチェアなどにも安定して座らせることができるため、大人も落ち着いて体を洗う時間がとれます。一方、この頃の赤ちゃんは、いろいろなものに興味を示し、何でも口に入れたがる時期。シャンプーやせっけんをなめたりしないように気をつけ、顔についたときにはガーゼなどで拭いてあげましょう。
6カ月を過ぎる頃になると、赤ちゃんの体つきにも安定感が出てきます。少しならひとりでおすわりができるようになる子も。生後9カ月頃〜10カ月頃には、ハイハイやつかまり立ちが安定し、つたい歩きをする子もいます。この頃になると、赤ちゃん自身も体のバランスが取れるようになり、ワンオペお風呂も少しラクになります。
赤ちゃんも大人も徐々にお風呂に慣れてくる時期ですが、油断は禁物。動きが活発になる頃は、転倒に注意が必要です。浴室内ではバスチェアに座らせて洗ったり、滑り止めマットを準備したりしましょう。また、危険なものは赤ちゃんの手の届かない場所にしまっておき、ボトルのキャップ類など飲み込んでしまいそうなものは放置しないようにしましょう。
1歳を過ぎると、多くの子がつかまり立ちからあんよをするようになります。赤ちゃんをバスタブのふちにつかまり立ちをさせた状態で洗ってあげられるようになると、ワンオペお風呂もさらにラクになります。赤ちゃんとのバスタイムが楽しめるように、やりやすい方法で工夫してみましょう。バスチェアもそろそろ卒業のタイミング。
つかまり立ちができるようになる頃から、浴室内での転倒に加え、溺水対策を万全に。浴槽のお湯は少なめに張るようにします。大人が髪を洗うときなどには赤ちゃんを浴槽から上がらせ、浴室内には滑り止めマットを敷きましょう。また、子供が小さなうちは、入浴後にお風呂のお湯を抜くことを習慣にすると安心です。

ワンオペお風呂をスムーズに終わらせるには、あらかじめ手順や導線をしっかりイメージしておくことが大切です。まずは基本の流れを確認しておきましょう。
お風呂に入れる時間帯に決まりはありませんが、極端に遅い時間は避け、できれば毎日同じくらいの時間に入れてあげると赤ちゃんの生活リズムも整いやすくなりますよ。
【ワンオペ風呂の基本の流れ】
1.脱衣所・浴室内を温める
2. 入浴後に必要なものを準備する
3. 温度は38℃~39℃くらいを目安にお湯を張る
4. 赤ちゃんが安全に待機できるスペースを確保する
5. 赤ちゃんを待機させているあいだに、大人の体や髪を洗う
6. 赤ちゃんの体を洗う
7. いっしょにお風呂から上がる
8. お風呂上がりのスキンケアをする
9. 赤ちゃんの着替えをする
以下にそれぞれの手順を詳しく説明していきます。
赤ちゃんは体温を調節する機能がまだ充分に発達していません。脱衣所や浴室が冷えているようなら、あらかじめ温めておきましょう。赤ちゃんが快適な室温の目安は、冬期は20℃〜25℃、夏期は外気温より4℃〜5℃くらいとされています。
バスタオル、赤ちゃんと大人の着替えやスキンケア用品などを準備しておきます。赤ちゃんの服は、着る順番に重ねておくとお世話がスムーズです。
大人には少しぬるいと感じるくらいが赤ちゃんにとっての適温。冬場は湯温が下がりやすいため、寒いようなら入ったときにお湯を足して調節しましょう。
バスマットやバスタオル、バウンサーなどの上で赤ちゃんが待機できるスペースを確保します。浴室のドアの前、脱衣所など、大人が入浴中でも目視で安全が確認できる場所を選びます。
赤ちゃんの服を脱がせて待機させ、大人が先に浴室に入って体や髪を洗います。赤ちゃんが寒くないよう、タオルなどをかけておくと良いでしょう。浴室のドアは開けたままにして、ときどき赤ちゃんに声をかけてあげると、ひとりで待っている間も安心できますよ。
赤ちゃんを浴室に入れて、顔→頭→おなか→手足→おしりの順に洗います。洗い終わったら手桶などでせっけんをよく流し、いっしょに湯船につかりましょう。浴槽の中では、大人の膝に赤ちゃんを乗せるなどして、しっかりと抱っこしてください。お湯につかる時間は冬場なら3分〜4分、夏場なら2分〜3分程度。体を洗う時間を含めて入浴時間は10分〜15分以内が目安です。
お風呂から上がり、赤ちゃんをタオルで包んでバスマットなどに寝かせ、手早く大人の体を拭きます。サッと羽織れるバスローブなどがあると便利。その後で赤ちゃんの頭と体をよく拭いてあげましょう。
ベビー用の保湿剤などで、赤ちゃんの肌を保湿します。月齢が低い赤ちゃんの場合、ベビー用の綿棒などでおへその水分を拭き取ってあげましょう。
スキンケアが終わったら、おむつや肌着、パジャマなどを着せて「ワンオペお風呂」終了です。大人もこのタイミングでお肌の保湿を忘れずに!
慣れないワンオペお風呂を少しでもラクに、安全に行うために活用したいグッズをご紹介します。先輩ママ・パパにも人気のバスチェアやバスマットをはじめ、あると便利なオススメ用品をセレクト。お子さまの成長に合わせてお気に入りを選び、安心・安全を心がけながら赤ちゃんとのバスタイムを楽しんでみてはいかがでしょうか。
お風呂場や脱衣所で、赤ちゃんを座らせておけるお風呂用チェア。首すわり前からでも使えるものがあると便利。リクライニングして体が洗えるタイプなら、赤ちゃんもリラックスできそう。
オススメをセレクト!
『はじめてのお風呂から使えるバスチェア』(アップリカ)

推奨年齢:新生児〜2歳頃まで
3段階に背もたれの角度を調節できるバスチェア。フルリクライニングにすると新生児から使えます。柔らかマットとフロントガードが付いた安心設計。小さくたためてコンパクトに収納できます。
※画像引用元:
「Aprica」商品紹介ページ
おすわりや立っちができるようになった赤ちゃんを浴槽の外で洗うときには、寝かせたり座らせたりして洗える赤ちゃん用のバスマットを用意しましょう。転倒防止にも役立ちます。
オススメをセレクト!
『ひんやりしないおふろマットR』(リッチェル)

推奨年齢:新生児〜生後6カ月頃まで
くぼみがあって安定感があり、お尻の部分にお湯を入れて使うこともできます。寝かせたまま赤ちゃんの頭や体を洗えるため両手がふさがらないのでお世話もスムーズ。ママやパパが体を洗う間も、寝たまま待たせることができます。発泡素材で温かな使用感。軽くて持ち運びも便利です。
※画像引用元:
「Richell公式ウェブショップ」商品紹介ページ
おすわりができるようになったら、浴室内に敷くフラットタイプのマットを用意しておくのがオススメです。マットの上にすわらせたまま、体を洗うことができますよ。また、つかまり立ちをはじめたら、浴槽内に敷く滑り止め用マットがあると安心です。お風呂の中で遊ぶときに、足やお尻を滑らせてしまうリスクを抑えられます。
オススメをセレクト!
『ラバーすのこ』(オーエ)
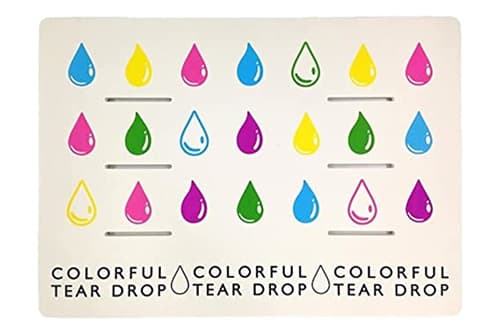
推奨年齢:生後1カ月〜
丈夫でずっしりと厚く、防カビ加工が施されたEVA樹脂で作られたお風呂マット。ラバータイプで滑りにくく、裏面に凹凸があるため安定感があります。バスチェアなどを乗せてもOK。
※画像引用元:
「Amazon」商品紹介ページ
赤ちゃんを抱っこしながら洗うときには、プッシュすると泡で出てくるベビーソープがあると便利。赤ちゃんの肌に優しい成分でできた泡切れの良いものなら、デリケートな肌にも負担をかけません。使い勝手が良く、肌タイプに合うものを見つけたら、シャンプーやスキンケアも同じラインで揃えておくと◎。
オススメをセレクト!
『ベビー全身泡ソープ』(ピジョン)

推奨年齢:新生児〜
皮脂をとりすぎず、潤いを残して洗いあげる泡ソープ。弱酸性・無着色・無香料・パラベンフリーで0カ月から使えます。泡シャンプーやお風呂上がりのスキンケアも同ラインで揃っています。
※画像引用元:
「Pigeon」商品紹介ページ
お湯に触れただけで正確な湯温を把握するのは難しいもの。慌てて入って「熱い!」なんてことになっては大変です。赤ちゃんが生まれたら、一つあると重宝するのが湯温計。お風呂に慣れない沐浴のときから使ってみてはいかがでしょうか。
オススメをセレクト!
『タニタ 湯温計』(タニタ)

推奨年齢:新生児〜
お風呂に浮かせて使う湯温計。壁にかけて浴室の温度を測ることもできます。季節ごとの適温がひと目でわかるラインつきで便利。
※画像引用元:
「TANITA」商品紹介ページ
お風呂上がりの赤ちゃんの髪も体も拭くことができるフード付きバスタオル。素早く全身の水分を拭き取って湯冷めを防いでくれます。大人もバスローブが1枚あれば、お風呂上がりにサッと羽織ってすぐに赤ちゃんのお世話に取りかかれます。
オススメをセレクト!
『ベビーバスローブ バスポンチョ』(今治タオル)

推奨年齢:新生児〜4歳頃
洗濯しても柔らかな風合いが長続き。赤ちゃんの肌にも優しい綿100%で、高い吸収性の赤ちゃん用バスローブ。エコテックス認証の湯冷め防止機能付き。
※画像引用元:
「Amazon」商品紹介ページ
「お風呂が嫌い!」「入りたくない!」そんなときにもお気に入りのおもちゃがあれば、お風呂タイムが楽しくなるかもしれません。低年齢の赤ちゃんには、誤飲しない大きめのサイズのものや、ジョウロなどシンプルで安全なものを選びましょう。
オススメをセレクト!
『くるくるシャワー』(サッシー)

推奨年齢:6カ月〜
水をかけるとビーズがぷかぷか、プロペラがクルクル回ったり、下の穴から水がちょろちょろシャワーのように流れたり。赤ちゃんは水の動きに興味津々!カラフルで赤ちゃんにも持ちやすいデザインも魅力です。知育効果も期待できそうなバス&プールトイ。
※画像引用元:
「DADWAYオンラインショップ」商品紹介ページ
何かと慌ただしいワンオペお風呂タイムでは、大人のスキンケアが手抜きになりがち。とくに、産後すぐのママは体調やホルモンバランスの変化などによってシミやくすみなどの肌トラブルが現れやすい傾向にあります。時短スキンケアで効率よく、きれいな肌をキープしたいもの。最近では、化粧水・乳液・保湿クリームが1つになったオールインワンジェルも人気。また、シートマスクで保湿ケアしながらお風呂上がりのお世話をしたという先輩ママも多いようです。忙しい子育て中も、工夫しながら健やかな肌をキープしましょう。
オススメをセレクト!
『アクアベール スペシャルマスク』(資生堂)

ここぞのときの速攻マスク。たっぷりの美容液成分が含まれたぷるっとした密着シートで、角層のすみずみまでにうるおいがジュワッと浸透。「化粧水・乳液・クリーム・マスク・美容液・アイマスク」の1品6機能。洗顔後、これ1枚でスキンケアを完了してもOK。
※画像引用元:
「資生堂オンラインショップ」商品紹介ページ
子供がひとりでも大変なワンオペお風呂。ふたりの場合はどうするの?「下の子を洗っている間に上の子が脱走!」「自分が顔を洗うときもシャンプーのときも目を閉じられない!」など、下の子と上の子、そして自分も洗う「子供ふたりのワンオペお風呂」の負担はひとりのときの2倍以上という声も・・・。そんな、ワンオペ育児の難関をどのように乗り越えたら良いのでしょう。
ここでは、子供たちの安全を確保しながら、しっかり洗う手順とコツ、注意点をまとめました。今まさに悩んでいる方もこれからの人も、ぜひ参考になさってください。
脱衣所などに着替えスペースを作り、タオルやお着替え、おむつなど、お風呂上がりに必要なものを準備しておきます。タオル類は、お風呂から上がってすぐの場所に用意しておきましょう。
子供たちの衣服を脱がせて大人といっしょに3人で浴室に入ります。下の子は、バスチェアなどに座らせて待機させておきましょう。洗う順番は、上の子→大人→下の子が理想的。上の子を洗ったら先に湯船に入れ、全員が洗い終わったら一緒に湯船で温まります。安全のため、お湯は浅めに入れておき、子供から目を離さないようにしましょう。
3〜5分温まったら下の子と一緒に出て素早く自分と下の子の体を拭きます。上の子はもう少し湯船で待機。上の子を上がらせて体を拭きます。大人も子供もバスポンチョやバスローブがあるとベスト。
子供たちの体に保湿剤を塗ります。ふたりのお着替えが終わったら、この段階で自分も服を着ます。
2人同時のお風呂が大変なのも、我が子が小さなときだけのこと。ワンオペ育児で大変な時期は、いずれ終わります。気持ちを切り替え、工夫しながら少しでもラクに乗り越えられると良いですね。

最後に、ワンオペお風呂を安全に行うためのポイントと注意点について、あらためておさらいしましょう。
赤ちゃんから目を離さず、お風呂に入る導線をシミュレーションし、安全に入れるための事前準備をしてからお風呂に入りましょう。
生後2カ月くらいまでの赤ちゃんの場合、お風呂から上がった後にはおっぱいや育児用ミルクを与えましょう。生後6カ月以降で、授乳食がスタートしている赤ちゃんであれば、白湯(さゆ)や常温のベビー麦茶などで水分を補給しても◎。同じタイミングで、大人もしっかり水分補給しましょう。
赤ちゃんは、10cmくらいのちょっとした水位でも溺れる可能性があるとされています。浴槽のお湯は少なめにし、入浴後は湯を抜くなどの対策を徹底してください。また、首掛け式乳幼児用浮き輪はとくに注意。子供を浴槽に浮かせたまま自分の洗髪をしている際に事故が起きたケースが複数報告されています。浴室内に赤ちゃんがいる場合は、絶対に目を離さないようにしましょう。
※参照:
「Vol.497 首掛け式乳幼児用浮き輪は気をつけて使用しましょう!」消費者庁
赤ちゃんのお風呂を毎日ワンオペで行うのはとても大変なこと。何もかも完璧にひとりでこなそうとすると疲れてしまいます。ときにはベビーバスで赤ちゃんだけを入浴させる日があってもOK。また、赤ちゃんのお世話で忙し過ぎてママやパパがご自身のスキンケアや健康管理がおろそかにならないように気をつけてくださいね。無理をせず、手を抜く日があっても大丈夫。ラクな気持ちで辛い時期を乗り切りましょう。
さて、育児中はできるだけストレスをため込まず、心身の健康を保つことが肝心です。次の記事では、育児中のママ・パパのストレスや疲労の原因になりがちな「赤ちゃんの寝かしつけ」をテーマに、赤ちゃんが寝てくれない原因や、寝かしつけのテクニックなどについて詳しくご紹介していますので、ぜひご覧になってくださいね!













新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ

ずりばいは、いつから?時期やハイハイとの違い、練習方法、成長との関係などをご紹介

コップ飲みの練習はいつから?練習方法や期間、うまくいかないときのアドバイスも

赤ちゃんの白湯、いつからOK?5つのメリットと3つの注意点

赤ちゃんの麦茶はいつから?月齢別の飲ませ方やタイプ別の作り方の紹介

【専門家に聞く】メンタルリープはいつ?特徴や計算方法・ぐずり対策をわかりやすく解説

新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

ハイハイはいつから?早い子は5カ月頃?練習方法やしない原因、注意点をご紹介

いつから赤ちゃんを自転車に乗せられる?前乗せ?後ろ乗せ?抱っこ紐は?

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

赤ちゃんとのお散歩、いつからOK?最適な時間帯や注意点

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

英語の「美味しそう」は使い分けが大切!3つの異なる表現方法とは

お誕生日は英語メッセージで!1~3歳も英語でお祝いしよう!

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ
© Disney © Disney/Pixar
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and
E.H. Shepard.


新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ

ずりばいは、いつから?時期やハイハイとの違い、練習方法、成長との関係などをご紹介

コップ飲みの練習はいつから?練習方法や期間、うまくいかないときのアドバイスも

赤ちゃんの白湯、いつからOK?5つのメリットと3つの注意点

赤ちゃんの麦茶はいつから?月齢別の飲ませ方やタイプ別の作り方の紹介

【専門家に聞く】メンタルリープはいつ?特徴や計算方法・ぐずり対策をわかりやすく解説

新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

ハイハイはいつから?早い子は5カ月頃?練習方法やしない原因、注意点をご紹介

いつから赤ちゃんを自転車に乗せられる?前乗せ?後ろ乗せ?抱っこ紐は?

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

赤ちゃんとのお散歩、いつからOK?最適な時間帯や注意点

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

英語の「美味しそう」は使い分けが大切!3つの異なる表現方法とは

お誕生日は英語メッセージで!1~3歳も英語でお祝いしよう!

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ
