
新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン
よく調べられているキーワード

赤ちゃんの鼻水が止まらないと気になりますよね。どうやって取ってあげたら良いの?と悩むことも多いのではないでしょうか。
今回は、赤ちゃんの鼻水の正しい取り方や鼻水の原因、鼻吸い器(吸引器)の使い方など、ご家庭でできる対処法をアドバイス!鼻水と病気の関係についてもお答えします。
監修:田中純子先生(マーガレットこどもクリニック院長)
目次

2歳頃までの子供は、なかなか自分で上手に鼻をかむことができません。また鼻の機能も未発達なため、ちょっとした気温の変化やホコリなどにもすぐ反応して、鼻水・鼻づまりを起こしやすい状態にあります。鼻水が出たら次の方法をお試しください。
鼻水が出たら放置せず、清潔で柔らかいガーゼやティッシュでそっとふき取ってください。鼻水が続くと鼻の下があれたりただれたりしやすいので、強くふかないように注意しましょう。肌があれているときにはぬるま湯で絞ったガーゼで優しくぬぐい取り、ワセリンや保湿クリームなどを塗っておきます。
鼻水が固まって鼻がつまることもあります。蒸しタオルを鼻の上にあてたり、健康な場合はお風呂に入れたりすると蒸気によってつまりが緩和されます。固まってしまった鼻水は無理に取ろうとせず、綿棒やぬるま湯で絞ったガーゼなどを使って鼻の入り口だけ取るようにします。
鼻水の量が多くて、鼻がつまって赤ちゃんが苦しそうなときには、市販の「鼻吸い器」を使うとご家庭でも効率良く吸い取ることができます。鼻吸い器の購入は必ずしも必要ではありませんが、鼻がよくつまって眠りにくくなることをくり返すお子さんや、ゼイゼイしやすいお子さん、また中耳炎にくり返しなるお子さんにはオススメです。
ただし、器具をいやがる赤ちゃんも多いので、無理をせず、鼻水の量や体調をよく見極めながら使用してください。

赤ちゃんの鼻水を吸い取る「鼻吸い器」には主に、電動据え置きタイプ、電動ハンディタイプ、大人が口で吸い取る手動タイプの3種類があります。赤ちゃんの鼻に触れる先端部分は柔らかなシリコンや樹脂などの安心素材でできているものが主流です。吸引力やサイズ、お手入れのしやすさなどをポイントに、使いやすいものを選ぶと良いでしょう。
スイッチを入れ、ノズルを赤ちゃんの鼻にあてて吸い取ります。吸引力が強いので鼻の奥にたまった鼻水をスッキリ取り除きたいときにも便利。電池は不要のコンセントタイプです。部品を取り外して丸洗いできるものや洗浄するパーツが少ないタイプなど、お手入れしやすいものが人気。
手動タイプより強め、据え置き電動タイプより弱めの安定した吸引力で鼻水を吸い取るコードレスタイプの吸引器。赤ちゃんを抱きかかえながら片手で手軽に操作できます。先端のノズル部分は洗浄が可能で衛生面にも配慮されています。価格帯は据え置きタイプよりもリーズナブル。電池式やUSB充電式があります。
赤ちゃんの鼻にノズルをあてて、大人が息を吸う力で吸引する鼻吸い器のほか、スポイト式の手動タイプもあります。コンパクトで場所を取らずに使え、パーツを分解して簡単に洗浄できます。1,000円以下の手頃な価格で購入できるものが揃っています。
一般的に電動タイプは吸引力が強く、鼻水の量が多いときや鼻水が鼻の奥につまったときに速やかに吸い取ることができます。
一方、手動タイプは赤ちゃんの様子を見ながら大人が吸い取る力をコントロールできるので、初めてでも安心。吸引力は電動タイプより劣りますが、まずはお手軽に、ちょっとした鼻水を吸ってあげたい場合にオススメ。手頃な価格も魅力です。
吸引力と手軽さの両方を求めるのなら電動ハンディタイプを、手軽さは多少犠牲にしても、ネバネバした鼻水などをしっかり吸引してあげたい場合は据え置き電動タイプを選ぶと良いでしょう。
鼻水を吸引するタイミングは、入浴できる場合であればお風呂上がりがベスト。お風呂の湿気や蒸気によって鼻の奥の鼻水が取れやすい状態になってから行うとスムーズです。
鼻水を吸い取るときには、赤ちゃんの頭が動かないように固定できる体勢で行います。ノズルの先端を鼻の穴と水平になるようにゆっくり差し入れ、鼻の粘膜を傷つけないように注意しながら吸引しましょう。
どのタイプも勢い良く吸引しすぎないことが大事です。手動タイプの場合はママ・パパが息を吸う力や吸引する力を調節し、電動タイプであれば弱いレベルからはじめます。また、一度に取り切ろうとして長時間使用するのもNG。1日1〜2回を目安に手早く行いましょう。
鼻吸い器は機種によって使用方法が異なるため、取扱説明書に従って正しく行なってください。
鼻の中はとてもデリケート。ノズルを深く入れすぎると刺激によって鼻血が出てしまうこともあるので十分気をつけてください。赤ちゃんがいやがるときには強引に吸い取らず、機嫌の良いときを見計らってケアしてあげましょう。

赤ちゃんの長引く鼻水の原因で一番多いのは風邪です。風邪をひくと、赤ちゃんは大人よりも咳や鼻水が長く続くことが多く、鼻水は平均して2週間前後続きます。ときには1カ月ほど続くこともあります。さらに保育園や幼稚園に通いはじめると、風邪をくり返しひきますので、結果として年中、鼻水をたらしているお子さんも少なくありません。鼻水がたれていても、元気があって苦しそうな様子がなければ経過を見ても大丈夫です。年齢が大きくなってくると、風邪をひきにくくなります。
新生児の場合には鼻の空間が狭いために少しの鼻水で鼻がフガフガ鳴ったりすることがあります。また、よく吐き戻す子はミルクや唾液の逆流で鼻水が続いたり、鼻がゴロゴロ鳴ったりすることもあります。こうした場合でも、母乳やミルクが飲めていて、体重がきちんと増えていれば問題はありません。
スギやヒノキなどの花粉やダニ・ハウスダストなどが鼻に入ると、アレルギー体質のお子さんは鼻水が続くことがあります。
実は、赤ちゃんでも2歳を過ぎた頃から花粉症を発症することがあるので注意が必要です。毎年春先に鼻水が長引いて、目や鼻がかゆいなどの症状があるようなら、一度医療機関で相談しましょう。
鼻水と関係のある病気の1つに中耳炎があります。中耳炎は、鼓膜の奥にある中耳が炎症を起こす病気です。耳の痛み、耳だれ、発熱などの症状が見られます。中耳炎は、鼻水が耳管に入り込む、もしくは耳管が炎症を起こすことなどが原因と考えられています。大人と比べ、赤ちゃんの耳管は短くて水平になっているため、鼻水が入りやすく中耳炎になりやすいといえます。
中耳炎を予防するには、長引く鼻水を放置せず、鼻の奥にたまった鼻水をこまめに吸い取ってあげることが大切です。
赤ちゃんの鼻水は心配のないものが多く、風邪をひいても症状が軽ければ急いで病院へ行かなくても大丈夫です。鼻水は、病気を治すために鼻の中の異物や外敵を排出するときに出る自然な反応で、薬などで無理やりとめる必要はありません。
生後3カ月以上の赤ちゃんの場合、熱も38度未満で生活に支障がなければ、しばらく家で安静にしながら様子をみてください。

赤ちゃんの鼻水は心配のないものが大半ですが、以下の症状がある場合は小児科か耳鼻咽喉科を受診しましょう。
・38度以上の発熱が続き、元気がない。
・咳きこみがあり、ゼイゼイしたり夜間眠れないことが続く。
・鼻づまりがひどく、母乳やミルクが飲みにくそう。
鼻水の色については、黄緑色=細菌感染のように考えられがちですが、風邪の治りかけでも濃い色になることはありますし、仮に細菌感染があったとしてもそのほかの全身の状態が良好であれば、必ずしも抗生物質は必要ありません。全身の状態が良ければ、鼻水が黄色いという理由で受診する必要はありません。
いざ小児科か耳鼻咽喉科を受診するときのために、家や保育園・幼稚園などの近くに信頼できる専門医や薬局を見つけておくと良いでしょう。
また最近では、病気の診療に加え、育児に関する相談やオンライン診療を行う医療機関も増えています。いつでも気軽に受診できるところをあらかじめチェックしておくと安心です。
いかがでしたか?ズルズルと鼻水が出たり、鼻がつまったりして苦しそうな赤ちゃんを見ると「大丈夫かな?」と心配になりますが、鼻水は、異物や外敵から身を守るための自然な反応であることがわかりました。最近では、鼻水を自宅で吸引できる便利な器具が市販されています。
まずは、無理なくご家庭でできる範囲でホームケアをしてあげましょう。成長に合わせて、少しずつ自分で鼻をかむ練習をしていけると良いですね。
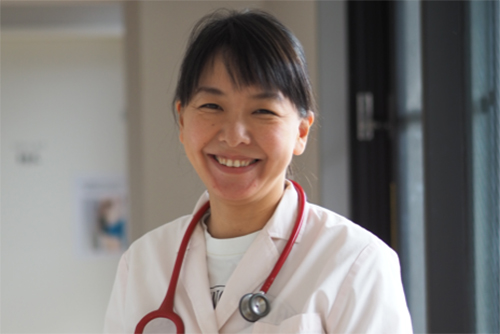
監修:田中 純子(たなかじゅんこ)先生
マーガレットこどもクリニック院長。千葉大学医学部卒業、同大学院医学薬学府博士課程終了後、小児クリニック勤務を経て、2017年にマーガレットこどもクリニック開業。一般診療のほか、オンラインや電話による診療、また子育て相談も行う。二児の母。
マーガレットこどもクリニック













新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ

ずりばいは、いつから?時期やハイハイとの違い、練習方法、成長との関係などをご紹介

コップ飲みの練習はいつから?練習方法や期間、うまくいかないときのアドバイスも

赤ちゃんの白湯、いつからOK?5つのメリットと3つの注意点

赤ちゃんの麦茶はいつから?月齢別の飲ませ方やタイプ別の作り方の紹介

【専門家に聞く】メンタルリープはいつ?特徴や計算方法・ぐずり対策をわかりやすく解説

新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

ハイハイはいつから?早い子は5カ月頃?練習方法やしない原因、注意点をご紹介

いつから赤ちゃんを自転車に乗せられる?前乗せ?後ろ乗せ?抱っこ紐は?

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

赤ちゃんとのお散歩、いつからOK?最適な時間帯や注意点

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

英語の「美味しそう」は使い分けが大切!3つの異なる表現方法とは

お誕生日は英語メッセージで!1~3歳も英語でお祝いしよう!

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ
© Disney © Disney/Pixar
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and
E.H. Shepard.


新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ

ずりばいは、いつから?時期やハイハイとの違い、練習方法、成長との関係などをご紹介

コップ飲みの練習はいつから?練習方法や期間、うまくいかないときのアドバイスも

赤ちゃんの白湯、いつからOK?5つのメリットと3つの注意点

赤ちゃんの麦茶はいつから?月齢別の飲ませ方やタイプ別の作り方の紹介

【専門家に聞く】メンタルリープはいつ?特徴や計算方法・ぐずり対策をわかりやすく解説

新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

ハイハイはいつから?早い子は5カ月頃?練習方法やしない原因、注意点をご紹介

いつから赤ちゃんを自転車に乗せられる?前乗せ?後ろ乗せ?抱っこ紐は?

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

赤ちゃんとのお散歩、いつからOK?最適な時間帯や注意点

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

英語の「美味しそう」は使い分けが大切!3つの異なる表現方法とは

お誕生日は英語メッセージで!1~3歳も英語でお祝いしよう!

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ
