
新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン
よく調べられているキーワード

日中、夜中に関わらず新生児・赤ちゃんが突然うなることがあります。赤ちゃんがうなる理由には、母乳やミルクの飲み過ぎ、就寝の体勢や環境、おなかに便やガスが溜まっていることなどがあるようです。
ここでは赤ちゃんがうなる原因と対処方法などを紹介します。
監修:藤田秀樹先生(目黒通りこどもクリニック院長)
新生児や小さな赤ちゃんのうなり声を気にするママ・パパは意外に多く、「日中や明け方などにうー、うーとうなる」「夜中に突然うーん、うーんとうなる」「顔を真っ赤にしていきみながらうー、うーとうなり声をあげる」など、1カ月健診での相談も少なくないようです。
中には授乳の後や入眠時など、決まった時間にうなる赤ちゃんもいます。また、手足をバタバタさせたり、うなりながら暴れたりする子もいて、赤ちゃんによって状況はさまざまです。いつ、どのようなときにうなるのかを観察していると、ある程度パターンが見えてくることもあります。
「苦しそうだけど大丈夫?」と心配になりますが、いずれもこの頃の赤ちゃんに多く見られる生理現象のひとつで、それほど珍しいことではありません。

赤ちゃんはなぜ突然うなったり、いきみ声をあげたりするのでしょう。言葉にできない不快感を訴えているような場合には、対策が必要です。
以下ではその原因と対処法を、「新生児期から生後3カ月頃」と「生後4カ月から生後6カ月頃」の2つの発達段階に分けて解説します。
※個人差があるため、月齢はあくまでも目安です。
新生児期から生後3カ月頃の赤ちゃんは、まだ寝返りができず、運動量も少ない時期。また、消化器官が十分に発達していない上に排泄にも慣れていないため、おなかに便やガスが溜まりやすい状態にあります。この頃の赤ちゃんがうなる主な原因と対処法をみていきましょう。
昼と夜の区別がつかない新生児期の赤ちゃんは、眠りが浅く、半分覚醒したような状態で「うー、うー」と声を出すことがあります。生理現象のひとつなので、過度に心配する必要はありません。ちょっとした環境変化で目を覚ましたり、空腹やおむつの汚れなどによる不快感からうなったりすることもあります。
対処法:おなかの空き具合やおむつ汚れはこまめに確認しましょう。眠りが浅くてうなっているような場合は、直射日光を避けたり、照明の明りやテレビ・ラジオの音などに配慮したりするなど、赤ちゃんが気持ちよく眠れる環境を整えることも大切です。
生後3カ月頃までの赤ちゃんは、吸啜反射(きゅうてつはんしゃ)※により、母乳やミルクを与えられるだけ飲んでしまい、飲み過ぎてしまうことがあります。授乳直後にぐずったり泣いたりしているのを見て、「飲み足りないのでは?」と必要以上に与えてしまうと、苦しくてうなり声をあげることがあります。
対処法:授乳後、赤ちゃんが顔を真っ赤にして苦しそうにうなったり、おなかがぱんぱんに張っていたりする場合は、母乳・ミルクを飲み過ぎている可能性があります。
授乳の後に頻繁にうなる、吐き戻すようなら、飲ませる量を見直したり、調整したりして様子を見てください。授乳量について心配な場合は、かかりつけの医師・助産師などに相談しましょう。
※ママの乳首など、口に入ってきたものを強く吸う反射。哺乳反射とも呼ばれる赤ちゃんの原始反射のひとつ。
授乳時に、母乳やミルクといっしょに飲み込んだ空気を上手に吐きだせず、不快感からうなることがあります。授乳後にうなるようなら、胃の中に空気が溜まった状態で苦しがっていることが考えられます。
とくに、寝返りがうてない時期は、ゲップをうまくだせずに手足をバタバタさせたり、暴れたりしながらうなる赤ちゃんもいます。
対処法:授乳の後、ゲップが出なくて苦しそうにしていたら、赤ちゃんを縦抱きにして背中をさすってみましょう。空気を押し上げるように下から上に向かって行うのがポイントです。
それでも出ないときには、背中を軽くトントンとたたいてみます。赤ちゃんの背中をできるだけ伸ばすように支えるなど、少し姿勢を変えるだけでゲップが出ることもあります。
胃や腸などの働きが未発達なこの頃の赤ちゃんは、おなかにガスが溜まりやすく、いきんでうなることがあります。一方、生後2カ月〜3カ月頃になって消化器官がある程度発達すると、腸内に便を溜めることができるようになります。そのため便秘になりやすく、うんちをだそうとしてうなり声をあげることも。顔を真っ赤にしていきんでいる場合や、おなかが張っているときは便秘の可能性も考えられます。
対処法:おなかにガスが溜まって苦しそうなときは、おなかに「の」の字を描くように優しくマッサージしてみましょう。また、両方の足首を握って膝を軽く曲げ伸ばしする「足の体操」も効果的。下肢を動かして腹圧をかけるようにすると、腸が刺激され、おなかに溜まったガスや便が出やすくなります。
マッサージや体操は、満腹時を避け、授乳前やお風呂上がりのおむつ替えのときなどがオススメです。なお、何日も便が出ていなくて、いきんでうなる場合は便秘の可能性も考えられます。おなかが張って苦しそうなら、綿棒浣腸などで排便を促してあげるのもひとつの方法です。
生まれて間もない赤ちゃんは、吸う力も弱く、母乳やミルクを上手に飲めないことがよくあります。おっぱいのくわえ方や授乳姿勢に何らかの問題があって、飲みづらくて授乳中にうなっているのかもしれません。また、生後2カ月〜3カ月頃になると、母乳・ミルクの味がわかるようになり、味が気に入らなくてうなる赤ちゃんもいます。
対処法:授乳の際には、ママにも赤ちゃんにも負担が少ない授乳姿勢を心がけることが大切です。母乳の場合、横抱き、縦抱き、フットボール抱きなど、いろいろ試してみることをオススメします。ママのおっぱいの状態も大切です。
授乳前に専用のオイルなどで乳頭マッサージをすると、乳頭が柔らかくなって赤ちゃんが吸いやすくなりますよ。
一方、ママの食べたものや体調によって、母乳の味も微妙に変化します。赤ちゃんが好む味はサラサラで甘味のある母乳といわれていますが、脂っぽいものを食べすぎたり、ストレスが溜まっていたりすると、苦味や酸味が強くなるなど母乳の味が低下することがあります。高脂質・高カロリー食品はできるだけ避け、栄養バランスの良い食事を心がけましょう。
育児用ミルクの場合も、メーカーによって味が異なるため、赤ちゃんの好みに合わないようならメーカーを変えてみるのもひとつの方法です。
・室温・湿度・服装に注意
まだ言葉が喋れない赤ちゃんは、不快感を上手に表現できません。体温調整が苦手なこの時期の赤ちゃんは、暑さ・寒さなどの不快感からうなることがあります。部屋の温度や湿度(冬期は20〜25℃、夏期は外気温より4〜5℃低いくらい、湿度はいずれも50〜60%くらい)が適切かどうか、着せ過ぎていないかなど、室内環境や服装、寝具などにも注意しましょう。
・運動したい・お話がしたい
同じ場所で寝たり起きたりを繰り返している赤ちゃんは、体を動かしたくてうなることがあります。長時間、同じ場所・同じ姿勢で過ごしているときに、手足を動かしながら「う〜」とうなったりするのは、運動をしたいからかもしれません。機嫌が良いときなどに、手足を軽くマッサージしたり、抱っこしたり室内を歩いたりしてみましょう。また、単純に声を出すのが楽しくてうなることもあるようです。赤ちゃんの声に応えるように、優しく話しかけてあげて下さい。

生後4カ月を過ぎる頃になると、首がすわり、寝返りをうつようになるなど赤ちゃんの運動量が増える時期。
また生後6カ月頃から離乳食が始まると、発育環境にも大きな変化が見られます。この時期に赤ちゃんがうなる原因として、離乳食開始で母乳・ミルク摂取量が減ったことによる水分不足、離乳食の消化不良などが考えられます。
母乳やミルクを飲んでいる時期は、赤ちゃんに必要な水分量も足りていますが、離乳食が始まると、哺乳の量も少しずつ減るために水分が不足しがちになります。その結果、便が硬くなったり便秘になったりすることがあります。
また、のどが乾いてうなることもあるようです。とくに汗をかきやすい季節は、脱水症状にも注意が必要です。理由が思い当たらないのに不機嫌なうなり声をあげたり、泣いても涙が出なかったりするようなときには水分不足や脱水症の可能性があります。
対処法:離乳食がスタートしたら、白湯やベビー用麦茶などで不足した水分を補うようにしましょう。食事や外出時、お風呂上がりなどにも水分を補給してあげると良いでしょう。夏場など、よく汗をかく季節には、脱水症状に注意が必要です。スプーンや哺乳瓶、マグなど、月齢に合った器具で飲ませてあげましょう。
また、離乳食にりんごのすりおろし、バナナ、さつまいものペーストなど、食物繊維が豊富なメニューを積極的に取り入れるようにすると、便秘の予防に効果があります。ヨーグルトなど、乳酸菌を含んだ食品にも、お通じが良くなる作用が期待できます。
母乳やミルクを飲んでいた赤ちゃんに離乳食を与える際は、量・食材・形態などに工夫が必要です。離乳食の開始によって腸の働きが変化し、消化不良を起こす子も少なくありません。また、ガスや便が溜まりやすくなり、おなかの不調からうなり声をあげることがあります。
対処法:離乳食は、お米のおかゆ少量からスタートし、様子を見ながら野菜、くだもの、豆腐など、徐々に種類を増やしていきます。未消化などによる下痢が見られるようなら、食材・量・形態などの見直しや、母乳やミルクを欲しがるだけあげるなど、その時々で調整するようにしましょう。
なお、離乳食開始の目安は、一般的には生後5カ月〜6カ月といわれていますが、赤ちゃんの成長や発達には個人差があります。体調や消化の状態などを確認しながら、赤ちゃんのペースに合わせて無理なく進めることが何より大事です。
生後4カ月以降になると、首がすわって寝返りができるようになる赤ちゃんもいます。寝返りによっておなかや胸、肺などが圧迫されて苦しくなり、うなり声を上げることがあります。
対策:最初のうちは、寝返りをうっても自分の力で元に戻ることが出来ない子も多くいます。窒息などのトラブルを防ぐためにも、寝返りをしてうつぶせの状態になってしまったら、苦しくなる前に仰向けに戻してあげてください。
とくに就寝時は、こまめに様子を確認するなどの注意が必要です。こども家庭庁では、1歳になるまで赤ちゃんを仰向けで寝かせることを推奨しています。
※参考:
「乳幼児突然死症候群(SIDS)について」こども家庭庁
・離乳食の味が気に入らない
離乳食がスタートすると、赤ちゃんの味覚も徐々に発達しはじめます。月齢が進むにつれ、離乳食の味が気に入らない、おいしく感じないためにうなることがあるようです。
赤ちゃんが好む味は、ミルクや母乳にも含まれている「甘味」と「旨味」といわれています。逆に「酸味」や苦味」は、離乳食を開始したばかりの赤ちゃんにとっては苦手な味。生後5カ月〜6カ月頃に与えたい食材の中では、トマト、みかん、プレーンヨーグルトなどに酸味が多く含まれ、レタスや春菊などに苦味が含まれています。
嫌がるようなら、加熱して酸味や苦味を和らげるなど、調理法を工夫してみると良いかもしれません。味が気に入らないだけでなく、中には手で掴みたいのに思い通りにいかず、うなって不満を訴えている場合もあります。
こうした欲求は、食べ物に興味を示し始めたしるしでもあります。離乳初期は、食べられる食材や調理法が限られていますが、いろいろな食感や風味を体験させながら、食事の時間を楽しめるようにしていきましょう。
・成長に伴う反応
生後5カ月頃になると、自分の声が聞こえてくるようになり、うなったり、声を出したりして遊ぶようになります。成長に伴った反応なので、ご機嫌な様子なら、ママやパパもその声に応えながらコミュニケーションを楽しんであげてくださいね。
・体調不良・発熱
風邪をひいた、発熱など、体調不良でうなり声をあげることもあります。体温が38℃くらいあっても、機嫌が良くて食欲もあるようなら、赤ちゃんが快適に過ごせるように着るものや室温・湿度を調節しながら少し様子を見ましょう。おなかが冷えているような場合は、ホットタオルなどで温めてあげるのも効果的です。

赤ちゃんがうなるのはよくあることですが、ご紹介した対処法で解決しない場合や、下記の様子がみられるようなら早めに受診しましょう。
・38℃以上の熱がある
・鼻水や咳が出る
・ぐったりして母乳やミルクが飲めない
・頻繁に苦しそうにうなる
また、呼吸が苦しそう、どこか痛そう、うなり方がいつもと違うなどの症状があるときには、速やかに医療機関を受診してください。
赤ちゃんが病気で受診する際は、まずは小児科に相談するのが良いでしょう。別の科で診察が必要な場合にも、小児科医から「耳鼻科で診てもらいましょう」「眼科が良いですね」など、案内してもらえます。
なお、症状が軽く、赤ちゃんを病院に連れて行くか迷ったときは、「こども医療でんわ相談※」を利用する方法もあります。全国同一の短縮番号『#8000』をプッシュすることで、お住まいの地域の医療相談窓口に自動転送され、小児科医・看護師から、赤ちゃんの状態に応じた適切なアドバイスを受けることができます。
※参考:
「こども医療でんわ相談」
赤ちゃんが昼夜を問わずうなる理由はいろいろで、個人差もあるようですね。はっきりとした原因がわからないケースもありますが、突然うなったり、暴れたりするのは、赤ちゃんが周囲の大人に何らかの不快感や不調を訴えているサインかもしれません。我が子をよく観察し、原因を見極めて対処してあげましょう。
さて、今回の記事でもご紹介したように、赤ちゃんがうなる原因のひとつとなるのが「便秘」です。実は、消化器官が充分に発達していない赤ちゃんは、大人に比べて便秘になりやすいといわれています。
次の記事では赤ちゃんの便秘について、その原因や特徴、家庭でできる対処法などについて詳しくご紹介していますので、ぜひご覧になってくださいね!
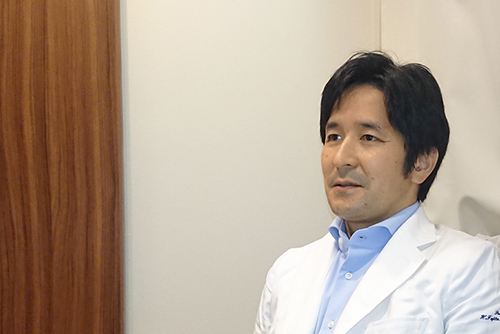
監修:藤田 秀樹(ふじたひでき)先生
目黒通りこどもクリニック院長。慶應義塾大学医学部卒業、同大学院医学研究科博士課程終了後、小児科勤務を経て、2014年より現職。子供の心と体の健康を目指す保育所「みんなのおうち」を併設。
目黒通りこどもクリニック













新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ

ずりばいは、いつから?時期やハイハイとの違い、練習方法、成長との関係などをご紹介

コップ飲みの練習はいつから?練習方法や期間、うまくいかないときのアドバイスも

赤ちゃんの白湯、いつからOK?5つのメリットと3つの注意点

赤ちゃんの麦茶はいつから?月齢別の飲ませ方やタイプ別の作り方の紹介

【専門家に聞く】メンタルリープはいつ?特徴や計算方法・ぐずり対策をわかりやすく解説

新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

ハイハイはいつから?早い子は5カ月頃?練習方法やしない原因、注意点をご紹介

いつから赤ちゃんを自転車に乗せられる?前乗せ?後ろ乗せ?抱っこ紐は?

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

赤ちゃんとのお散歩、いつからOK?最適な時間帯や注意点

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

英語の「美味しそう」は使い分けが大切!3つの異なる表現方法とは

お誕生日は英語メッセージで!1~3歳も英語でお祝いしよう!

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ
© Disney © Disney/Pixar
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and
E.H. Shepard.


新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ

ずりばいは、いつから?時期やハイハイとの違い、練習方法、成長との関係などをご紹介

コップ飲みの練習はいつから?練習方法や期間、うまくいかないときのアドバイスも

赤ちゃんの白湯、いつからOK?5つのメリットと3つの注意点

赤ちゃんの麦茶はいつから?月齢別の飲ませ方やタイプ別の作り方の紹介

【専門家に聞く】メンタルリープはいつ?特徴や計算方法・ぐずり対策をわかりやすく解説

新生児に与えるミルクの適切な量は?足りない、飲みすぎのサイン

ハイハイはいつから?早い子は5カ月頃?練習方法やしない原因、注意点をご紹介

いつから赤ちゃんを自転車に乗せられる?前乗せ?後ろ乗せ?抱っこ紐は?

【医師監修】新生児に快適な室温は?春夏秋冬の温度調節のコツと対策

赤ちゃんとのお散歩、いつからOK?最適な時間帯や注意点

新生児の期間っていつまで?新生児の特徴や乳児・幼児との違い

英語の「美味しそう」は使い分けが大切!3つの異なる表現方法とは

お誕生日は英語メッセージで!1~3歳も英語でお祝いしよう!

つかまり立ちはいつから?いつまで?平均時期と練習方法、安全対策をご紹介

しんどい睡眠退行はいつまで続く?月齢別の原因・特徴と乗りきるコツ
