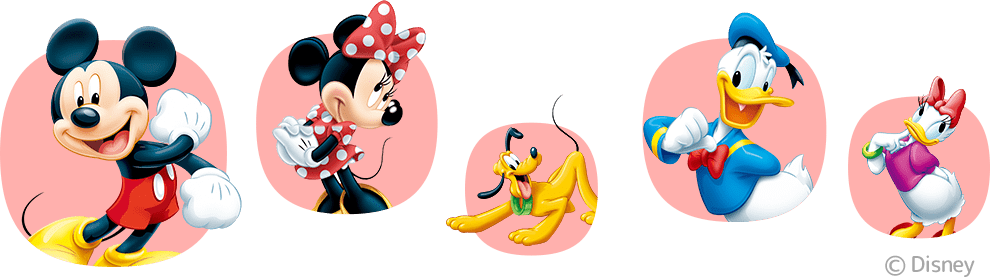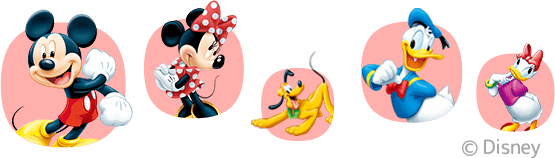成蹊大学・小野 尚美教授へのインタビューです!
英語教育がご専門の小野先生は、30年以上に渡って日本の英語学習者のための指導法の研究をされています。
近年、ニュージーランドを中心とした英語圏の国々で効果をあげているリーディング・リカバリー・プログラム(※)の理念と指導法を応用して、日本で英語を学ぶ児童・生徒の読み書き能力育成を目指す英語指導法を開発しておられます。
今回は、子どもが言葉を獲得するために望ましい方法や、早期に英語教育を始めるメリットについて、小野先生にご意見を伺いました。
※ リーディング・リカバリー・プログラム(Reading Recovery Program):
英語を母語としているけれども、英語の読み書きにつまづいてしまった児童の言語能力を回復させるために、一対一の集中的な指導で訓練する言語指導法。
ニュージーランドの言語教育学者マリー・クレーによって開発されたこのリーディング・リカバリー・プログラムは、英語を外国語として学ぶ児童の読み書き能力回復にも効果を上げている。
また、スペイン語やフランス語を母語とする児童の読み書き能力回復のための指導にも応用されている。
Q1.親が子どもの英語習得をサポートするにはどうすればよいでしょうか?
Q2.子どもの英語のインプットを増やすためにはどんな方法がありますか?
Q3.言葉の発達にはインタラクションが重要とのことですが、子どもにはどのように質問すればよいですか?
Q4.英語を学び始めるのに適した時期はいつでしょうか?
Q5.幼児英語教育を検討しているお母さん・お父さんたちへのアドバイスをお願いします。
Q1.親が子どもの英語習得をサポートするにはどうすればよいでしょうか?
どのような言語でも、子どもが言葉を使えるようになるには、インプットを増やしてあげることが大切になります。子どもに英語を習得させたいと思っていても、日本では英語のインプットの機会がどうしても少ないので、まずは英語を聞いたり、英語で書かれている本を読む機会を増やしてあげることが大切です。
もっとも英語がまだよくわからない子どもが英語で書かれた本を読むのは難しいので、最初は親や英語の先生が英語で書かれた絵本を読んであげるといいですね。
しかし、ただ単にインプットを与えるだけでは子どもの英語学習には助けになりません。英語で話したり書いたりなど、子どもが英語で何か表現する機会を作ってあげることも重要です。親や教師は、それぞれの子供が興味を持っていることや既によく知っている事柄に注目してあげて、子どもがそれを英語で表現できるように誘ってあげるとよいでしょう。
そのときには、完璧な英語で表現することを目標とするのではなく、何か英語で表現できたという達成感をもたせるように導いてあげることが大切です。そして子どもが英語で表現できたときには、しっかりほめてあげましょう。ほめてあげることで、子どもの学習は進みます。
Q2.子どもの英語のインプットを増やすためにはどんな方法がありますか?
会話の機会が少ない子どもは言葉の発育が遅いと言われるくらい、言葉の発達には人とのインタラクションが大切です。まずは親や教師が子どもに英語で話しかけて英語を使うように誘ってみましょう。
そして、子どもが好きなアニメやディズニ―のDVDを英語で見たり、日本語で見たことのあるテレビ番組の英語版を見せたりするのもよい方法です。
また、英語でストーリーを読み聞かせてあげることもよいでしょう。子どもが興味を持って聞けるようにインプットしてあげることが大切になります。子どもの目線に立って抑揚にも気をつけながら読んであげます。
インプットを与えるときには、ただ単にビデオを子どもに視聴させるといった音声によるインプットだけでは英語の知識はなかなか定着しないので、文字を見せながらお話の読み聞かせをして、視覚と聴覚の両方からインプットすることをおすすめします。
やがて英語で書くようになるときのために、音声とともに文字を見る機会を与え、英単語を認識する練習をさせていくことが大切なのです。音声だけでなく文字を見せながら英語で書く活動へとつなげていくことで、英単語や英語の文が記憶に定着しやすくなります。
例えばフィンランドでは、英語の字幕を流すテレビ番組が多く、国民の英語能力の育成に大きな成果を上げています。音声と文字の両方が言語学習には大切なのです。
また、海外の小学校では、子どもが英語を使って作成した作品や英語で書かれた標語を教室に貼り、子どもたちが常に英語に触れるような環境を整えています。これを生活環境図(environmental prints)と呼びますが、こうした身近に接する文字情報は言語の習得に大きな影響を与えるのです。
子どもの英語を使った作品を教室に貼って見せると、子どもは達成感があって英語学習への励みにもなりますね。
Q3.言葉の発達にはインタラクションが重要とのことですが、子どもにはどのように質問すればよいですか?
例えば、英語の習得を促すなら、英語で放送されているDVDを一緒に見て、英語の表現に注目させたり、面白そうな場面で子どもと一緒に英語で"That's interesting!"(それ面白い!)とか"It's really funny!"(本当に面白いね!)と言ってみたりして、一緒に英語を使ってみましょう。
また、子どもが知っていることを引き出す質問がよいですね。無理に子どもに教え込んだり、記憶させるのではなくて、興味を引き出してあげる聞き方をしましょう。必ずしも英語で質問しなくても大丈夫です。
お話の場面に応じて、子どもに「どう思う?」とか「どうしてこの主人公はこんなことをしたのかな?」「みんなだったらこんなことするのかな?」「この先どうなるのかな?」という風に聞いてみてください。
段階的に子どもの反応を引き出す質問を継続していくことも効果があります。「共感させる」、「意見を求める」、「話の内容を予測させる」、「話の内容と子どもの日常生活を関連づけさせる」ことを意識した質問を日本語で続けてみましょう。
特に、インタラクションの効果を上げるためには、子どもの好きなことや興味をもっていることをあらかじめ理解しておくことが大切です。
リーディング・リカバリー・プログラムでは、言語訓練を始める前にまずは教師が子どもに質問して、何が好きなのかを知るというように子どものことを理解するために「ウォームアップ」という時間をとります。もし子どもが絵を描くことが好きならば絵を自由に描かせて、何を描いているか聞く、色使いをほめてあげるなどして、コミュニケーションを取りやすい雰囲気作りをしておくと、その後の学習がうまくいくのです。
Q4.英語を学び始めるのに適した時期はいつでしょうか?
幼児期からの英語教育は子どもによい影響を与えると思います。特に幼児期から英語の音声に慣れ親しんでいると、その後の英語の音に対する反応がよくなると言われています。また幼児期から英語学習をすると、英語の母語話者に近い英語の発音が習得しやすくなります。
しかし、幼児期から学ばないと英語習得は難しいというわけではありません。一番大切なことは、子どもが英語を勉強したい、英語を使ってコミュニケーションすることは楽しいというように英語学習に興味を持って取り組んでいけるかということです。
最近の言語研究の分野では、「複言語・複文化主義」視点を言語教育に取り入れてみるという考え方が話題となっています。これは、個人が複数の言語を使ってコミュニケーションできる能力を養うと同時に、複数の文化理解能力をもつことで、文化や言語の異なる人々との相互理解に大いに役立つという考え方です。
外国の言葉に興味を持つということは、その言葉が使われている社会や文化について興味を持つようになるということです。複数の言語に興味を持つようになれば、様々な文化について学ぶことになります。複数の言語を学ぶことで、国際理解能力を養うことができるというわけです。
今や英語は、異なる言語を話す人々とのコミュニケーションのための重要な言語になってきています。英語学習がきっかけとなり、他の言語学習にも興味を持つようになる可能性も出てくるのです。
Q5.幼児英語教育を検討しているお母さん・お父さんたちへのアドバイスをお願いします。
英語を学ぶことは、母国語である日本語との違いを認識することでもあるため、英語学習は日本語学習につながるともいえます。また、Q4で述べましたように、英語を学習することで、母語だけでなく他の外国語学習にも興味を持つようになる可能性もあります。
幼い頃から英語に接して、言語やその背景にある文化の違いを学ぶことで、子どもは「英語ではこうした言葉の使い方をするとうまく相手に気持ちが伝わるんだ」とか「英語を母語とする人達にはこういうことを言うと傷つけることになるんだ」といったことを理解することができ、社会人として最も求められる「コミュニケーション能力」を身につけることもできるでしょう。
将来子どもが国際社会で活躍するために、英語学習を通して多様な文化を理解できる素地を作ってあげることは重要だと思います。
まとめ
多様な文化を理解できる豊かな人格を形成するために、幼児期からの英語教育は大きな助けとなりそうです。
今回のインタビューでは、言葉の発達におけるインタラクションの重要性と、どんな質問を子どもに投げかければ活発なインタラクションを生み出せるのかを伺いました。
また、言語学習の際は、話し言葉と文字を結びつけてインプットすることで知識の記憶への定着が高まるとのお話も伺いましたが、これは英語教材を使う際に意識しておきたいポイントですね。
なお、「ディズニーの英語システム」(DWE)のDVDやトークアロング・カードは、英語の音声と文字の対応が自然に理解できるようにつくられている教材ですので、ぜひ活用してみてください!

プロフィール:小野 尚美(おの なおみ)
成蹊大学文学部英米文学科教授。
津田塾大学学芸学部国際関係学科卒。
1987年、米国インディアナ大学大学院言語学部応用言語学科修士課程修了(M.A.取得)。
1992年、米国インディアナ大学大学院教育学部言語教育学科博士課程修了(Ph.D取得)。
1993年、昭和女子短期大学部英語英文学科専任講師。
1998年、昭和女子大学短期大学部英語英文学科准教授。
2004年より現職。
著書に、『英語教材を活かす―理論から実践へー』(共著・朝日出版社)、『小学校英語から中学校英語への架け橋 文字教育を取り入れた指導法モデルと教材モデルの開発研究』(共著・朝日出版社)、『教室英語ハンドブック』(共著・研究社)、『「英語の読み書き」を見直す Reading Recovery Program研究から日本の早期英語教育への提言』(共著・金星堂)、『言語科学の百科事典』(共著・丸善株式会社)、『英語の「授業力」を高めるために-授業分析からの提言-』(共著・三省堂)、『応用言語学事典』(共著・研究社)、『リーディング事典』(共著・研究社)、高等学校英語検定教科書『World Trek-English Reading』(共著・桐原書店)、『Reading as Inquiry:A New Horizon for ESL Learners』(単著・リーベル出版社)など。